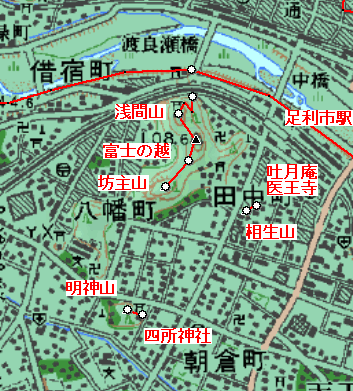| 【明神山】標高 96.2m |
|
四所神社
東武伊勢崎線の足利市駅の西を南北に走る県道36号線を
南に向かいます。
足利市民プラザを通過し、朝倉3丁目の交差点を右折し、
大麦ダクワーズで有名になったロアを過ぎると、
左側に花屋があります。
そこを左折すると、右の小高い場所に建つのが四所神社です。
鳥居や手水のある場所から数十段程度の石段を上ると、
立派な社殿が建っています。
足利市の重要文化財ともなっている四所神社は、出雲大社の祭神である大己貴命(おおなむちのみこと)を始めとする4つの祭神が祀られています。ということで、変わった名称の神社です。
内部には、扉には昇り竜、下り竜、鯉の滝上り、滝下りの絵が描かれていたり、柱や梁などの彩色が施されていたというが剥落しているようです。大きな絵馬があることは確認できました。
現在の社殿は、江戸後期の弘化4年(1847)に再建されたものです。
この神社のある裏山が明神山です。
古墳でもあるので明神山古墳と呼ばれています。
古墳時代後期の円墳33基と小前方後円墳1基からなる群集墳です。横穴式石室や埴輪があったことがわかっていますが、
現在はその殆どが失くなってしまっています。 |



|
|
|



|
岩場
社殿の左後ろから山頂へは、岩場の斜面を登ってゆきます。
よい感じの岩場です。
岩場の途中に高さ5、60cmのコンクリート製で屋根が赤、壁が白に彩色された小さな祠が岩の上に建っています。何が祀られているのかはわかりません。
その右後ろの岩の上には、
石碑と崩れかけた石祠があり、
石碑には、「男体山大権現」、両脇に「瀧尾山」、「太郎山」と記されています。栃木県らしい石碑です。 |
|
|
|
明神山山頂
岩場から木立の道に変わり、すぐ山頂です。
灌木に囲まれた山頂からは、
さっき走ってきた道路、
北には、浅間山、
そしてこれから登る坊主山、相生山が木々の間から望めます。 |





|
|
|


|
下山
山頂からは、社殿の右へ下る道を降ります。
「日露戦役記念碑」と記された石碑、
木の根元にやはり崩れかけた石祠が残っています。 |
|
|
| 【相生山】標高 33.9m |
|
吐月庵医王寺
足利市駅方向に戻り、
サイゼリア、切通しを過ぎ、すぐ右に曲がります。
そこに「子育観世音菩薩」と記された、
数本の朱い幟がたなびき、
「吐月庵医王寺」、「子育馬頭観世音」の2本の門柱が立つ緩い斜面の上に医王寺があります。
本堂には、坂東28番 子育観世音、如意輪観世音、馬頭観世音」と記された額が掲げられています。
本堂の右には、比較的新しい大きな地蔵、
左に多くの石仏、石塔が並んでいます。
その中のひと際大きい石碑が馬頭観音。
そこから岩場の斜面が山頂に向かっています。
岩場のところどころに立てられている新しい地蔵様が山頂へ誘導するように並んでいます。 |





|
|
|
 |
相生山山頂
地蔵の並ぶ急な岩場を登ってゆきます。
冬は落ち葉が敷き詰められ、地面が見えないので注意!
広場となっている山頂には、
ガスレンジ等のゴミが転がっていました。
木々の間から、西向いの坊主山、浅間山が見えます。 |
|
|
| 【坊主山】標高 54.9m |
|
八雲神社
通りに出て、北に100mほど戻り、
右にマンションのある交差点を左に入ると、
その先の山麓に八雲神社の鳥居が見えます。
森高千里の歌に登場する「八雲神社」ではありませんが、
足利にある八雲神社のひとつです。
こちらの八雲神社も地元の人たちに愛されてきた神社なのでしょうね。 |


|
|
|


|
富士の越へ
神社の左の石垣に沿って、坂を上ってゆきます。
途中民家のそばに「たなかちょう散策マップ」の案内が立ち、そのマップも持ち帰るように紙で置かれています。
さらに石垣の坂を進むと、
人家もなくなり、疎林の中の峠となります。富士の越です。 |
|
|
|
浅間山南参道、坊主山登山口
道路は八幡町へ下ってゆくのですが、
峠の右が浅間山の南参道、左が坊主山への道です。
以前浅間山を紹介したときには、
ここから八幡町へ下り、八幡山古墳へと歩いています。 |


|
|
|


|
山道
ここからは、灌木の山道らしい山道です。
先のふたつの山に比べると、
ちょっと山歩きらしい感じになりますが、数分で山頂です。 |
|
|
|
坊主山山頂
山名板も木にくくりつけられており、明るい山頂です。
灌木に囲まれていますが、
その間から隣りの浅間山の朱の社殿も見えます。
道は、さらに先の八幡町の方へ続いています。
足利の渡良瀬川の南の朝倉町、田中町の里山を歩いてみました。
いずれも子供の遊び場に適した里山です。
しかし、いまはそんな子供たちもいないでしょうね。 |



|
|
|
| ホーム > 足利 > 朝倉、田中の山々 明神山、相生山、坊主山 |
| |
|
|